
自己効力感とは、ある課題や目標に対して「自分ならできる!」という自信や期待を指します。同じ能力を持っていたとしても、自己効力感が高いか低いかでビジネスの成果は大きく変わってきます。そこで本記事では、マネージャーとして知っておくべき自己効力感の概要や社員の自己効力感の育て方などを解説します。
自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは何か?
自己効力感(一般性セルフ・エフィカシー)とは、ある具体的な状況で自分が適切な行動を行い、目的を達成できるという予想や確信のことを言います。カナダの心理学者アルバート・バンデューラ氏が提唱した概念であり、ビジネスの現場はもちろん、産業カウンセリングや予防医学、精神医療、教育の場面など、幅広い分野でその重要性が認識されています。
自己効力感は「結果予期」と「効力予期」の2つに区分されます。
- 結果予期:ある行動がどのような結果を生み出すのかという予測
- 効力予期:ある結果を生み出すために必要な行動を自分がどのくらいうまく行えるかという予測
たとえば、プロジェクトをタイトな日程で成功させなければならない場合、人はこれまでの経験値、自分の能力への自信などを総動員して結果を予測します。自己効力感が高い人材は、プロジェクトが成功するという確信のもと取り組み、自信をもって物事を判断していくため、厳しい状況下にあっても良い結果を出す傾向があります。
自己効力感が高い人と低い人の思考・行動パターン
自己効力感が高い人の思考や行動パターンにはいくつか特徴があります。
- 問題に直面したとき「できそうだ」と思う
- 困難な状況でも簡単にあきらめず努力することができる
- 腹痛や不眠、不安など心理的ストレスからくる不調を引き起こしにくい
- ストレスフルな状況にも耐えられる
一方で、自己効力感の低い人の思考や行動パターンにも特徴があります。
- 何か始めるとき「うまくいかないだろう」という発想が浮かぶ
- 能力をほめられても安易に信じられない
- 自分に自信がないため必要以上に他人に貢献する
- 怒り、不安、頭痛、腹痛など心因性の不調を起こしやすい
自己効力感が低い人は、自分の判断に自信がなく迷いがちです。また、人の意見に左右されがちです。そのため能力がありながら、判断を誤り成果を出せない傾向があります。
自己効力感が高いか低いかはチェックできる
自己効力感は自尊心や持って生まれた各自の自己肯定感とは違い、体験により変化します。科学的に研究された概念であり、すでに多数の臨床データが出ているため、簡易的な質問シートで自己効力感が高いか低いかをチェックすることが可能です。
たとえば、自己効力感を測定できる検査のひとつ「GSES(一般セルフ・エフィカシー尺度)」があります。質問項目は16個、所要時間が約3分と時間をかけず気軽に試すことができます。GSESで個人の認知的傾向や自己効力感の高低を測定できます。その結果を社員教育や職場のメンタルヘルス対策に活用することが可能です。
社員の自己効力感を高めるマネジメントとは?
自己効力感は客観的に測定できて高めることができるため、ビジネスに活用しやすい概念です。社員の自己効力感が高まると、行動が前向きに変わり、良い成果につながりやすくなります。管理職が自己効力感の意味を理解すれば、部下それぞれの自己効力感の高低に応じたマネジメントも可能となります。また、自分自身が日ごろ部下に対して自己効力感を下げていないかもチェックできるようになります。
どのようなマネジメントが部下の自己効力感を下げるのか?
マネジメントの難しさの一つに、同じ指導をしても相手によって受け止め方が違う点があります。相手の自己効力感の高低を理解すれば、それに応じた指導が可能となります。
たとえば、部下の仕事の完成度が80点だと感じた場合、自己効力感の高い部下に対しては、できていない20%の部分のみ指摘しても相手はそれを前向きに受け入れる可能性が高いです。しかし、自己効力感の低い社員に対して不足している点のみを指摘すると、さらに相手の自己効力感を下げてしまいかねません。このように自己効力感が低い社員には、まず完成度の高い80%の部分を評価しアドバイスすることが有効です。
ほかにも部下の自己効力感を下げかねない発言や態度があります。
- できていない点、不足している面のみを指摘する
- できなかった原因を必要以上に分析させる
- 以前の失敗やミスを蒸し返す など
仕事上のミスを指摘することは大事ですが、必要以上にそこに意識を向けさせると自己効力感の低いタイプの部下は失敗を心理的に再体験し、さらに自己効力感を下げてしまう可能性があります。
社員の自己効力感を高めるマネージャーのあり方とは?
成果を上げた社員に対しては、成果そのものを評価すれば、自然に相手の自己効力感は高まります。ただ、成果をそれほど上げていない社員に対しては、結果ではなくプロセス面での努力などをさりげなく認めることが大切です。
たとえば、以下のようにプロセスや成果以外の能力に触れる声かけを意識します。
- 「よく勉強している、よく知っているね」
- 「いつも丁寧な仕事をするね」
- 「責任感がある」
- 「頑張っているね」 など
成果を出していなくても、本人が業務上で地道に努力している面を言葉に出してほめることが鍵です。上司が自分の長所や頑張りを理解し長い目で見てくれていると認識すると自己効力感が高まります。
社員の自己効力感を高めるための施策
自己効力感の提唱者バンデューラ氏によると、自己効力感を高めるための方法は4種類あります。
- 自己の成功体験:実際の成功体験を積むこと
- 代理的体験:身近な他人の成功例に触発されること
- 言語的説得:身近な人間から自分に対する肯定的な言動を受けること
- 生理的状態:アルコールなど外部からの刺激を受けること
ビジネス現場では1~3までの方法を活用できます。仕事の成功体験を積ませること、身近に成功モデルがいる環境に社員を投入し「自分もできそう」と感じてもらうこと、上司や同僚など周りの人間が当人の人間性や能力を肯定的に評価し、それを言語で伝えることなどが有効です。
この中で、最も効果的なのは自己の成功体験です。本人にとってやや無謀な目標を成し遂げることで自己効力感は高くなるため、社員をチャレンジングな目標に挑戦させることが有効です。しかし、その場合失敗するリスクもあります。失敗した際に必要以上に自己効力感を下げさせないためには、チャレンジを是とし、ある程度失敗を許容するカルチャーの醸成も必要となります。
たとえば、あるアパレルメーカーの経営者は創業から急成長期に、あらかじめ年度の予算に社員がチャレンジし失敗した場合のコストを組み込んでいたと著書で述べています。プロジェクトであれ仕事であれ、何割かは必ず失敗します。そこを直視したマネジメントの在り方です。
自己効力感を高めるための研修も有効
社員の自己効力感を高めるには外部研修も有効です。管理職はもちろん、社員自身が自己効力感について理解することで、各自のセルフモチベーションを促すことが可能になります。
研修例として、以下のようなものがあります。
- 部下の自己効力感を高めるための管理職コーチング研修
- 社員個人が自己効力感について学び、自分で高めるノウハウを学ぶ研修
- お互いの長所を誉めたたえる研修
まとめ
自己効力感は、その人の物の見方、意欲、仕事への取り組み方に大きな影響を与えます。社員の自己効力感を高めることはモチベーション向上、生産性の向上、離職率の低下などいろいろな効果が期待できます。自己効力感についての知識を学び現場で活用していきましょう。


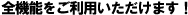






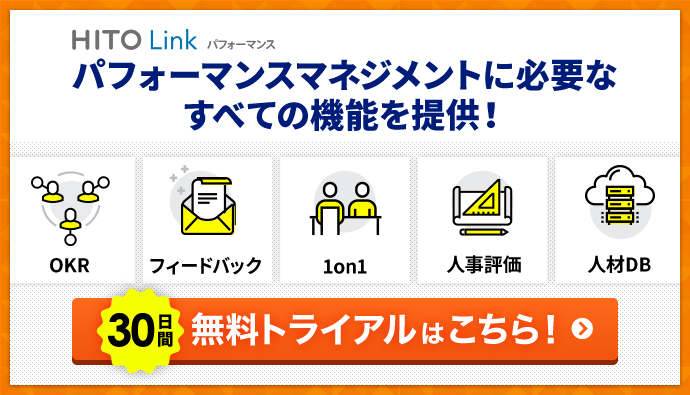




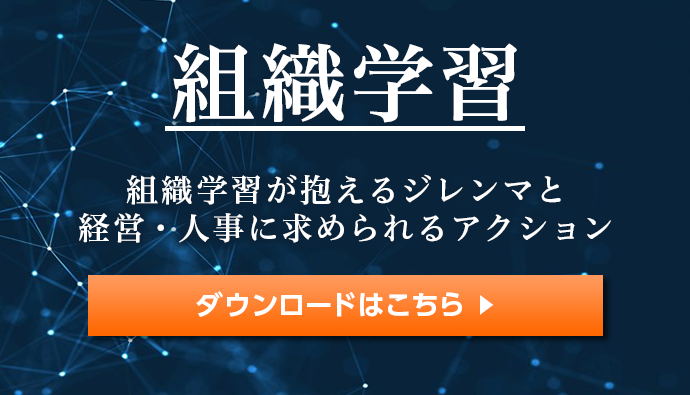
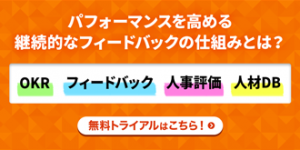
.png?width=300&name=HITO-Link%20Rec_B_Illust%20(1).png)




